-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年1月 日 月 火 水 木 金 土 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
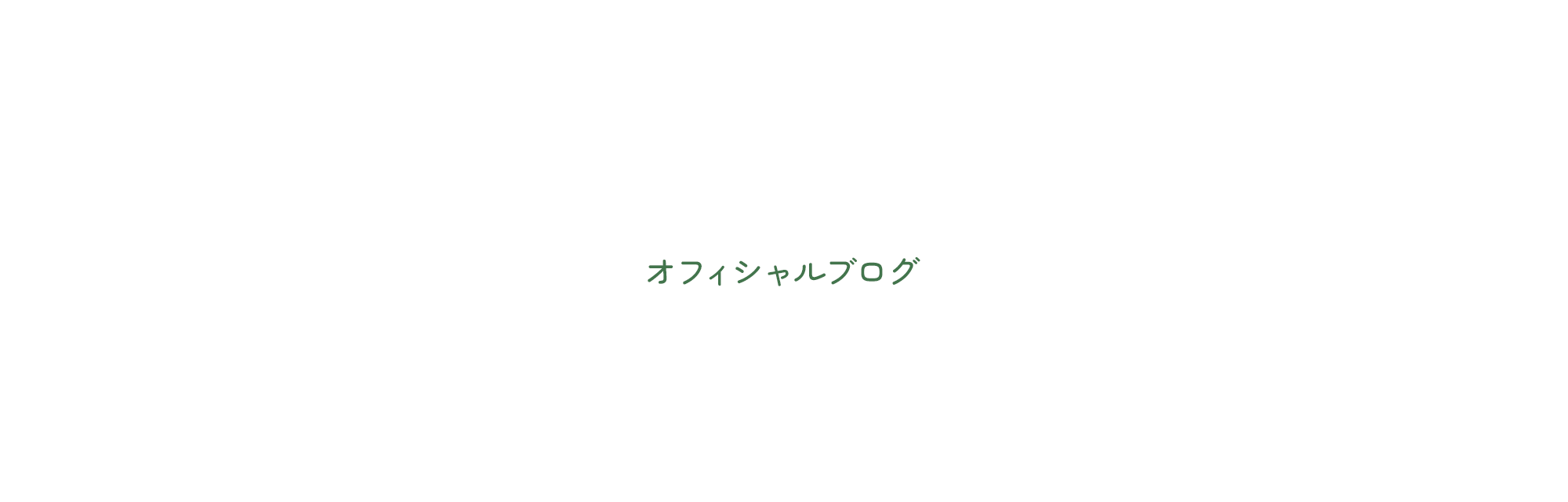
皆さんこんにちは!
山村農園、更新担当の中西です。
~“株が資産”~
ニラは多年性。つまり、株=資産です。定植→株養成→刈取りローテ→休ませて再生——このサイクルを静かに回せば、収量と品質は安定します。今日は年間設計/土と水/刈取りの勘所/病害虫IPM/予冷と出荷を“現場でそのまま動く型”にまとめました。🧭
目次
2–3月:圃場準備(pH矯正・堆肥)/育苗または株分け
3–4月:定植→浅植え・鎮圧→初期灌水たっぷり
5–6月:株養成(刈取りは控えめ)/除草を早期に
7–9月:本格刈取りシーズン(高温対策)
10–12月:刈取り継続/ハウスは保温/株更新の準備
1月:強剪定+休眠管理(地域により)
露地・施設で作型が変わります。“株を疲れさせない”優先で設計。🌿
目安pH:6.0–6.5。酸性が強いと生育ムラ&先枯れが出やすい。
物理性:通気>保水。高畝+明渠で根の酸欠を防止。
堆肥:10aあたり1t前後を基準に、土質で調整。未熟堆肥は厳禁。🌾
株分け苗/セル苗いずれも浅植え(クラウンが少し見える程度)。
条間40–60cm、株間15–25cmを目安(機械・手収穫で調整)。
初期の刈取りは欲張らない:定植後1回目は軽め、2–3回目で基礎体力をつける。
好適:昼18–25℃/夜10–18℃。
高温期はハウスで遮光20–30%+側窓全開、葉先焼け回避。
低温期は換気しつつ過湿回避(露は病気の入口)。
灌水:朝多め→夕切り上げ。過湿は根腐れ・軟弱徒長に。
追肥:少量多回。N過多は香りがぼけ・病気増。KとCaで葉の腰を作る。
施設は日射比例給液が基本。ドレインや土壌ECを週次でチェック。
収穫目安:葉長28–35cm、葉色と腰で判断。
刈り高さ:クラウンから3–5cm上を残す(芽点保護・再生確保)。
刈取り後:灌水→追肥→病害虫チェック。連続刈り過ぎない(株の休み週を入れる)。
代表例:さび病・葉枯れ・べと/ネギアザミウマ・ハダニ
基本策:
風通し(過密回避・適切な刈り上げ)
防虫ネット+粘着板(黄/青)で飛来抑制
潅水ムラの解消(乾湿差がストレスに)
薬剤はラベル遵守・ローテーション・収穫前日数厳守📒
花茎は別品目として高単価。抽苔期の管理をカレンダー化。
収穫はつぼみ膨らみ〜開花前。曲がり少・白濁なしを優先。
予冷:0–5℃・高湿で“畑熱”を抜く(冷風直撃は×)。
包装:穴あき袋+吸湿紙で結露を抑制。長さ28–32cmで整えると売場映え◎
規格:100g/200g束、花ニラ150gなど。名札・採収日・保存温度を明記。
☐ pH/EC・潅水ログの更新
☐ 刈り高さ(3–5cm)・連続刈り回避
☐ 風通し・遮光・換気設定
☐ 病害虫トラップのカウント
☐ 予冷温度・結露の有無
☐ 規格長・束重量の検品
まとめ
“株を休ませる勇気”ד刈り高さの一貫”ד水肥の薄く多回”。この3点で、ニラは静かに長く稼いでくれます。まずは**刈り後のルーチン(灌水→追肥→点検)**を紙に固定しましょう。🌱🤝