-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年1月 日 月 火 水 木 金 土 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
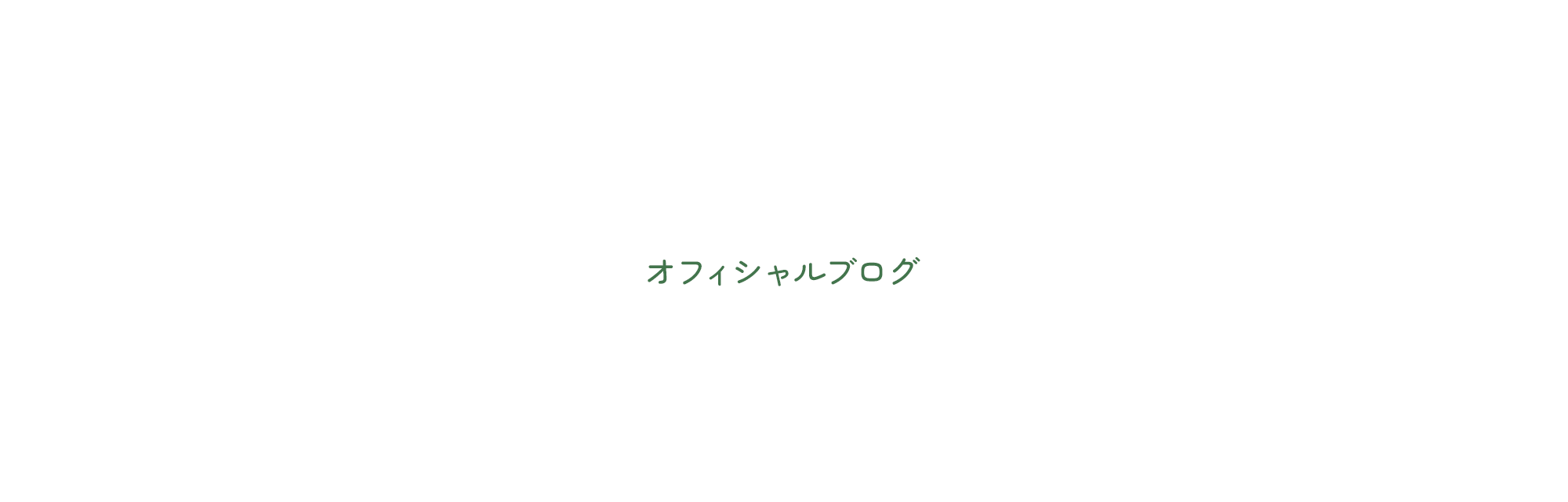
皆さんこんにちは!
山村農園、更新担当の那須です。
本日は第6回ニラ雑学講座!
今回は、「ニラ農園のこだわり~美味しいニラを育てる秘訣」について詳しくご紹介します。
山村農園では、香り高くシャキシャキとした食感のニラを一年中お届けするため、土づくりから収穫、出荷まで徹底した品質管理を行っています。家庭菜園をされている方にも参考になるポイントを盛り込んでいますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
山村農園では、化学肥料だけに頼らず、牛ふん堆肥や鶏糞堆肥などの有機質肥料を主体に使用しています。有機質肥料は土中の微生物活動を活発にし、土に自然な通気性と保水性をもたらします。特にニラは根が深く張るため、ふかふかで通気性の良い土壌が生育を大きく左右します。毎年秋には堆肥をすき込み、冬の間にゆっくりと分解・熟成させることで、春先の追肥を最小限に抑えられるよう工夫しています。
ニラは弱酸性から中性(pH6.0~7.0)を好みます。山村農園では定期的に土壌検査を行い、pHが6.0を下回る場合は苦土石灰を散布して調整。逆にpHが7.5を超えるようなアルカリ寄りになった場合は、ピートモスや腐葉土を追加して酸度を調整しています。適正なpH環境を保つことで、ニラの根張りが良くなり、肥料成分の吸収率もアップ。結果として、葉の厚みや色艶に大きな違いが出ます。
ニラは乾燥に弱く、葉がかたくなったり香りが飛んだりしますが、一方で過湿になると根腐れを起こしやすいデリケートな野菜です。そこで、山村農園では「表土が乾いてからたっぷり灌水」のサイクルを徹底。灌水は朝の涼しい時間帯に行うことで、日中の蒸散で土中に適度な湿度を保ちます。夏場は夕方にも軽く水をかけ、夜間の乾燥を防止。家庭菜園では、土の表面だけでなく指先で5cmほど掘って湿り気をチェックすると失敗が少ないですよ。
畝(うね)は高めに作り、畝間には幅10cm程度の溝を設けて余分な雨水が流れ出るように設計。特に梅雨や台風シーズンには、この溝がないと畝が冠水し根腐れの原因になります。さらに、雨が強い日は不織布を被せて土壌の跳ね返りを防ぎ、葉に泥はねがつかないように工夫。泥はねは病原菌の温床となるため、見た目だけでなく病害防止にも効果的です。
黒マルチフィルムを敷くことで、雑草の発生を大幅に抑制。雑草に栄養を奪われずに済むだけでなく、土壌温度の上昇を抑えて根の活性を維持します。さらに、マルチの端を埋め込む際には、空気の通り道を少し残しておくことで土壌中のガス抜けを確保。これにより、根が酸欠になるのを防ぎ、健康的に育ちます。
化学農薬に頼らず、テントウムシやヒメテントウなどの天敵を放飼してアブラムシを自然に制御しています。初期段階で被害を発見した場合は、ニンニクエキスや唐辛子エキスを原料とした自家製防除剤を散布。これらは人畜無害で、収穫後の風味にも影響を与えません。また、植え付け時にマリーゴールドを混植することで、線虫やアブラムシを寄せ付けにくくする効果も。見た目も華やかになり、一石二鳥です。
収穫はすべて手刈り。機械刈りではどうしても均一性が失われがちですが、手作業なら細すぎる葉や傷んだ葉をその場で取り除けます。刈り取りのタイミングは、朝露が乾いた午前中。湿った状態で刈ると傷みやすいため、乾燥したタイミングを見計らって行います。
刈り取ったニラはすぐに冷水にくぐらせ、表面温度を下げる「初期冷却」を実施。その後、低温倉庫(約2℃)で保管し、収穫当日のうちにチルド便で発送します。これにより、スーパーに並ぶまで約3~4日経っても、採れたての香りと食感を維持。お客様からは「シャキッとした歯ごたえが違う」「料理に入れた瞬間、ニラの香りが部屋中に広がる」と好評をいただいています。
有機質肥料とpH調整で土づくりを徹底し、根の張りを良くする。
適度な水やりと排水管理で乾燥と過湿のバランスを保つ。
マルチ栽培&生物防除で無農薬・低農薬を実現し、安全安心なニラを栽培。
手刈り収穫&チルド出荷で、香りと食感を損なわずお届け。
これらのこだわりを持つ山村農園のニラだからこそ、豊かな香りとシャキシャキの食感を一年中お楽しみいただけます。次回は「ニラを使ったおすすめヘルシーレシピ3選」をお届けします。ダイエットや健康維持にぴったりのアイデア満載ですので、どうぞお楽しみに!
以上、第6回ニラ雑学講座でした!
次回の第7回もぜひお楽しみに!
![]()